信州大学の、本気で遊ぶゼミとは?
2015年01月31日
信州大学に、「本気で」「真剣に」遊ぶ、
ということをひたすらやっている講座があるらしいんです。
・・・私の学生時代には、ほとんどすべての授業は教室で、
だいたい半分眠りながら先生の講義を聴く、という授業でしたけど。
今は、いろんなかたちの授業があるらしいですもんね。
でもねぇ。真剣に遊ぶっていうのはねぇ。。。
ということで、早速、その教室に潜入してまいりました。
教室に集まっていたのは、学部も学年も様々な学生さんたち。
確かにみんな、とっても楽しそう。なんか、生き生きしているんですよね。
「考えるゼミ」という名前の講義でした。
教養部の講義なので、基本的には1・2年生が受講するものなんですが、
全ての学生さんたちに開かれていて、
どんな学部でも何年生でも受けられるんだそうです。
でも、内容がさっぱりわからな~い!
学生さんたちに「何をやっているの?」とたずねたところ、
「ラジオの番組を作っています。
スポンサー集めから、収録、編集までぜんぶ、自分たちでやっています。
大変だけど、とてもおもしろい。」
「天竜村へ行って、ゆべしというお菓子作りを体験させてもらったり、
一人暮らしのお年寄りのところにお蕎麦を届けるボランティアに参加させてもらったり。
村の皆さんとお話させて頂いて、いろんな人生観、ライフスタイルがあるんだなって。
村から帰ってくると、またすぐ行きたくなるんです。
村にムラムラしてます。」
「コイバナ、っていうイベントをやりました。
自分の好きなことについてひたすら語る、というイベントです。
好きなことを語る時って、みんな凄いエネルギーがあるんです。
だから、語るもの楽しいですけど、聴くのも楽しい。
パワーもらえました。」
「自分をデザインするっていうイベントをやりました。
自分の事を20分語る、というものです。
自分と向き合うことって、なかなか辛いことでもあるんですけど、
やってよかったと思います。
何より、こういうことを大学でできることが素晴らしいと思います。」
ほ~~~~。
つまり。
学生さんたちがやりたいことを、やりたいように、真剣にやる。
で、その体験を教室に持ち寄って、みんなでシェアする、
という授業なのですね。
ある学生さんはこんなふうに言っていました。
「ここにいる人たちはみんな、目が輝いている。
こういう機会を作ってくれて、
やりたいことを後押ししてくれたり、見守ってくれる先生に感謝しています。」
先生は、有路 憲一 准教授。
「真剣に、っていうのが大事なんですよね。
今の多感な時期に大事なのは、本気で何かをやることだと思うんです。
笑ったり泣いたり怒ったり・・・。
その回数ではなく、深度、深さが大事だと思うんです。
ぼくの授業は、特に何を教えているわけではないけれど、
この体験が10年後にじわじわっと、
ああよかったな、っておもってもらえるものだったらいいな、と思っています。
今すぐに使える知識ではなくて、
心の基礎体力というか、基礎になる筋肉みたいなものを、
この体験でつけてほしい。」
っておっしゃていました。
机の上での勉強だけが大事なんじゃない。
教科書やインターネットから得られる事だけが知識じゃない。
真剣に体験して、とことん考えて、いっぱい困って、いっぱい喜んで。
その中から得られるものを、みんなでシェアていくのも、大事な大事な勉強だ!
「本気で遊ぶゼミ」は、そういうとてもユニークな講座だったんですね。

ひとりひとりが、自分のやりたいこと、楽しいと思うことを、真剣に考えて、
しっかり歩みを進めているようで。
なんだかとっても嬉しくなりました。
みんな、頑張ってね!!
久しぶりに生き生きしている学生さんたちと触れ合ってヨコロビいっぱいの、
松本の調査隊員 塚原正子でした。
ということをひたすらやっている講座があるらしいんです。
・・・私の学生時代には、ほとんどすべての授業は教室で、
だいたい半分眠りながら先生の講義を聴く、という授業でしたけど。
今は、いろんなかたちの授業があるらしいですもんね。
でもねぇ。真剣に遊ぶっていうのはねぇ。。。
ということで、早速、その教室に潜入してまいりました。
教室に集まっていたのは、学部も学年も様々な学生さんたち。
確かにみんな、とっても楽しそう。なんか、生き生きしているんですよね。
「考えるゼミ」という名前の講義でした。
教養部の講義なので、基本的には1・2年生が受講するものなんですが、
全ての学生さんたちに開かれていて、
どんな学部でも何年生でも受けられるんだそうです。
でも、内容がさっぱりわからな~い!
学生さんたちに「何をやっているの?」とたずねたところ、
「ラジオの番組を作っています。
スポンサー集めから、収録、編集までぜんぶ、自分たちでやっています。
大変だけど、とてもおもしろい。」
「天竜村へ行って、ゆべしというお菓子作りを体験させてもらったり、
一人暮らしのお年寄りのところにお蕎麦を届けるボランティアに参加させてもらったり。
村の皆さんとお話させて頂いて、いろんな人生観、ライフスタイルがあるんだなって。
村から帰ってくると、またすぐ行きたくなるんです。
村にムラムラしてます。」
「コイバナ、っていうイベントをやりました。
自分の好きなことについてひたすら語る、というイベントです。
好きなことを語る時って、みんな凄いエネルギーがあるんです。
だから、語るもの楽しいですけど、聴くのも楽しい。
パワーもらえました。」
「自分をデザインするっていうイベントをやりました。
自分の事を20分語る、というものです。
自分と向き合うことって、なかなか辛いことでもあるんですけど、
やってよかったと思います。
何より、こういうことを大学でできることが素晴らしいと思います。」
ほ~~~~。
つまり。
学生さんたちがやりたいことを、やりたいように、真剣にやる。
で、その体験を教室に持ち寄って、みんなでシェアする、
という授業なのですね。
ある学生さんはこんなふうに言っていました。
「ここにいる人たちはみんな、目が輝いている。
こういう機会を作ってくれて、
やりたいことを後押ししてくれたり、見守ってくれる先生に感謝しています。」
先生は、有路 憲一 准教授。
「真剣に、っていうのが大事なんですよね。
今の多感な時期に大事なのは、本気で何かをやることだと思うんです。
笑ったり泣いたり怒ったり・・・。
その回数ではなく、深度、深さが大事だと思うんです。
ぼくの授業は、特に何を教えているわけではないけれど、
この体験が10年後にじわじわっと、
ああよかったな、っておもってもらえるものだったらいいな、と思っています。
今すぐに使える知識ではなくて、
心の基礎体力というか、基礎になる筋肉みたいなものを、
この体験でつけてほしい。」
っておっしゃていました。
机の上での勉強だけが大事なんじゃない。
教科書やインターネットから得られる事だけが知識じゃない。
真剣に体験して、とことん考えて、いっぱい困って、いっぱい喜んで。
その中から得られるものを、みんなでシェアていくのも、大事な大事な勉強だ!
「本気で遊ぶゼミ」は、そういうとてもユニークな講座だったんですね。

ひとりひとりが、自分のやりたいこと、楽しいと思うことを、真剣に考えて、
しっかり歩みを進めているようで。
なんだかとっても嬉しくなりました。
みんな、頑張ってね!!
久しぶりに生き生きしている学生さんたちと触れ合ってヨコロビいっぱいの、
松本の調査隊員 塚原正子でした。
噂の調査隊「日本一の田舎が伊那谷に!それってどこ?」
2015年01月29日
長野県自体が、田舎暮らしに憧れる人たちにとっては人気の場所なんですが、
もう少し小さい単位。
市町村を単位に田舎暮らし日本一を調査した人達がいるんです。
しかも、その日本一の田舎が伊那谷にあるんだとか…
今日は、その日本一の田舎を調査してきました。
あなたの思う「田舎」ってどんな所ですか?
それをふまえて、あなたの予想は?
久保さん、キッシーは、
「そこら中にそういう場所がありすぎて、どこって言えな~い」
と言うのが答えでしたが・・・
実際、そんな田舎のランキングをつけたのが、
宝島社の「田舎暮らしの本」の編集者の皆さん。
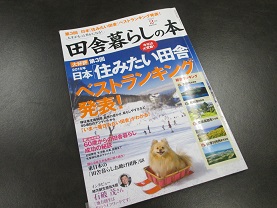
まずは、どんな趣旨で調査をし、どのようにランキングが出されたのか、
宝島社「田舎暮らしの本」の編集を担当していらっしゃる 菊地 駿 さんにお話伺いました。
菊池さんによると・・・
今回のランキングは「住みたい田舎ランキング」という事で、

田舎暮らしに関する、重要となるだろう項目を、全部で10ジャンル合わせて95項目の質問を用意して、そのアンケートを各自治体に郵送し回答してもらったもの。
実は長野県は、この雑誌でも「移住したい都道府県ランキング」で、
なんと9年連続の1位なんだそうで、

そんな人気県の中でも1位に輝いた自治体・・・
どこなのか、気になりますよね~
その自治体とは・・・・
伊那市 なんです。
伊那市ってちょっと意外じゃないですか?
でも、久保さんは「そうでもないよ~なんかわかる!!」と一言
実は、今回の日本一は、「子育てしやすい」という視点を重視した
「子育て世代にぴったりな田舎」ランキングで、伊那市が1位に輝いたんです。

ちなみに、伊那市は総合ランキングでも、長野県の中ではトップの7位。それに佐久市が続きます。
回答率は50%弱。
回答市町村の数は北海道に続いて、長野県は2位。多くの市町村が回答していました
さらに、「移住希望者お役立ちランキング」というものも出されているんですが、
そこでは長野県勢が大活躍!!
*お試し体験施設が多い 伊那市第1位(ダントツの27施設)
*移住相談会の年間開催数が多い 須坂市第1位 飯島町第3位 長野市第4位
*空き家の登録件数が多い 駒ヶ根市第2位
*クラインガルテンの区画が多い 松本市第3位
*田舎暮らし体験ツアーの年間開催数が多い 飯山市第3位
さすが、9年連続移住したい都道府県日本一の長野県。
ほとんど全ての項目に、長野県の市町村が顔を出していました。
ではそんな激戦区でなぜ、伊那市が1位になったんでしょうか?
菊地さんによると・・・
子育てのしやすさをベースに、就職支援、住宅取得に関する補助制度があるかなどの項目を設けて集計した結果、
伊那市は26点満点中、23点と最も多く、満遍なく移住者支援の体制が整っていると言えそうだ、という評価だったようです。
その中でも、教育環境が整っていて、独自の取り組みをしているのが、取材者の目には強烈に移ったらしく、
行政主導ではなく、地元住民が積極的に子供たちの教育環境を考えているのは、都会の人にとってはとても魅力的と
伊那市の小規模特認校「新山小学校」を例に挙げて話してくださいました。

こうやって聞いてみると、今回の日本一の田舎というのは、いわゆる人里離れた自然豊かで、ちょっとした不自由も楽しみのうちというような田舎ではなく、
「田舎に憧れる人達が移り住んで快適に田舎を楽しめる田舎」の日本一と言えそうです。
ですから、95の質問の中には、田舎暮らしに憧れる人達が一番求めている「自然の豊かさ」や「伝統的な文化や風土」ばかりでなく
「移住者を積極的に受け入れているか」とかスーパーやコンビニ、スポーツジムや温泉、インターネット環境まで、「日常生活」について整備がなされているか。
「交通の便がいいか」「老後の医療介護制度はどうか」など、田舎に住む私達が想像する田舎とは、少し違った視点も入っているんです。
では、この受賞、伊那市の人にとってはどうだったんでしょうか?
伊那市の集落支援員 水口航さんにお話し伺いました。
とにかく、伊那市の人にとっては「選ばれてビックリ!」と言うのが本当の所。
アンケートに答えた水口さんも、トップを取ろうと思ったわけではなく、あることをまとめて出しただけで、日本一になったと知らせをもらって、改めて何がそんなに良かったの?と改めて調べなおしたほどだったそうです。
取材に来たライターの方も、
「誰に聞いても、伊那市は子育てのまちだって言わないんですよね~」
と驚いていかれたそうです。
じゃあ、改めて「どうして?」と伺うと・・・
伊那小学校の話がまず飛び出しました。
チャイムもない、時間割もない、通知表もない(この通知表のないのはもう60年も前から)小学校。
総合教育を始めたのはもう40年の前の事。
地域が子供たちを育てる空気がすごく強いんだそうです。
そして、先ほども出た新山小学校。
全校生徒たった30人で、どこの地域からも入学できる学校です。
さらに、子育て支援センターには、20年も前から保育士さんが常駐していて、保育施設に行く前の子供たちの悩みに答えてくれる・・・
どれをとっても、昔から当たり前のようにやっていたことばかり。
それが、実は全国的に見ると、当たり前ではなくすごいことだった!という事なんですよね~
なんかとってもカッコいいですよね(^-^)
そして今回の受賞、意外な人達が反応しているそうなんです。
それは企業の経営者の皆さん。
ブログなどにこの事を、誇らしく書いてくれる方が多いそうなんです。
それは、伊那小学校のような教育を、今の子供のお父さんお母さんはもちろん、下手すればおじいちゃんおばあちゃんを飛び越えて、ひいおじいちゃん達の頃から受けて育っているんですね。(通知表がないのが、60年も前から続いてるっていう事からも、容易のそれは伺えますよね)
春になると教室はどこもガランとしていて、みんな春探しに野山をかけずり回ってる。
勉強の材料集めに町に出れば、アポなしでも、商店の人も、道行く人も、誰もが相手をしてくれる。
とにかく、地域で子供を育てているという感覚が根付いているのが伊那市なんです。
そのあったかい空気感が点数となって現れているのかもしれませんね。
今回の日本一の田舎とは、ど田舎ではなく、都会の人から見て暮らしやすい田舎の事でした。
伊那小で教育を受けてみたかった思っている 西村容子 でした♡
もう少し小さい単位。
市町村を単位に田舎暮らし日本一を調査した人達がいるんです。
しかも、その日本一の田舎が伊那谷にあるんだとか…
今日は、その日本一の田舎を調査してきました。
あなたの思う「田舎」ってどんな所ですか?
それをふまえて、あなたの予想は?
久保さん、キッシーは、
「そこら中にそういう場所がありすぎて、どこって言えな~い」
と言うのが答えでしたが・・・
実際、そんな田舎のランキングをつけたのが、
宝島社の「田舎暮らしの本」の編集者の皆さん。
まずは、どんな趣旨で調査をし、どのようにランキングが出されたのか、
宝島社「田舎暮らしの本」の編集を担当していらっしゃる 菊地 駿 さんにお話伺いました。
菊池さんによると・・・
今回のランキングは「住みたい田舎ランキング」という事で、
田舎暮らしに関する、重要となるだろう項目を、全部で10ジャンル合わせて95項目の質問を用意して、そのアンケートを各自治体に郵送し回答してもらったもの。
実は長野県は、この雑誌でも「移住したい都道府県ランキング」で、
なんと9年連続の1位なんだそうで、
そんな人気県の中でも1位に輝いた自治体・・・
どこなのか、気になりますよね~
その自治体とは・・・・
伊那市 なんです。
伊那市ってちょっと意外じゃないですか?
でも、久保さんは「そうでもないよ~なんかわかる!!」と一言
実は、今回の日本一は、「子育てしやすい」という視点を重視した
「子育て世代にぴったりな田舎」ランキングで、伊那市が1位に輝いたんです。
ちなみに、伊那市は総合ランキングでも、長野県の中ではトップの7位。それに佐久市が続きます。
回答率は50%弱。
回答市町村の数は北海道に続いて、長野県は2位。多くの市町村が回答していました
さらに、「移住希望者お役立ちランキング」というものも出されているんですが、
そこでは長野県勢が大活躍!!
*お試し体験施設が多い 伊那市第1位(ダントツの27施設)
*移住相談会の年間開催数が多い 須坂市第1位 飯島町第3位 長野市第4位
*空き家の登録件数が多い 駒ヶ根市第2位
*クラインガルテンの区画が多い 松本市第3位
*田舎暮らし体験ツアーの年間開催数が多い 飯山市第3位
さすが、9年連続移住したい都道府県日本一の長野県。
ほとんど全ての項目に、長野県の市町村が顔を出していました。
ではそんな激戦区でなぜ、伊那市が1位になったんでしょうか?
菊地さんによると・・・
子育てのしやすさをベースに、就職支援、住宅取得に関する補助制度があるかなどの項目を設けて集計した結果、
伊那市は26点満点中、23点と最も多く、満遍なく移住者支援の体制が整っていると言えそうだ、という評価だったようです。
その中でも、教育環境が整っていて、独自の取り組みをしているのが、取材者の目には強烈に移ったらしく、
行政主導ではなく、地元住民が積極的に子供たちの教育環境を考えているのは、都会の人にとってはとても魅力的と
伊那市の小規模特認校「新山小学校」を例に挙げて話してくださいました。
こうやって聞いてみると、今回の日本一の田舎というのは、いわゆる人里離れた自然豊かで、ちょっとした不自由も楽しみのうちというような田舎ではなく、
「田舎に憧れる人達が移り住んで快適に田舎を楽しめる田舎」の日本一と言えそうです。
ですから、95の質問の中には、田舎暮らしに憧れる人達が一番求めている「自然の豊かさ」や「伝統的な文化や風土」ばかりでなく
「移住者を積極的に受け入れているか」とかスーパーやコンビニ、スポーツジムや温泉、インターネット環境まで、「日常生活」について整備がなされているか。
「交通の便がいいか」「老後の医療介護制度はどうか」など、田舎に住む私達が想像する田舎とは、少し違った視点も入っているんです。
では、この受賞、伊那市の人にとってはどうだったんでしょうか?
伊那市の集落支援員 水口航さんにお話し伺いました。
とにかく、伊那市の人にとっては「選ばれてビックリ!」と言うのが本当の所。
アンケートに答えた水口さんも、トップを取ろうと思ったわけではなく、あることをまとめて出しただけで、日本一になったと知らせをもらって、改めて何がそんなに良かったの?と改めて調べなおしたほどだったそうです。
取材に来たライターの方も、
「誰に聞いても、伊那市は子育てのまちだって言わないんですよね~」
と驚いていかれたそうです。
じゃあ、改めて「どうして?」と伺うと・・・
伊那小学校の話がまず飛び出しました。
チャイムもない、時間割もない、通知表もない(この通知表のないのはもう60年も前から)小学校。
総合教育を始めたのはもう40年の前の事。
地域が子供たちを育てる空気がすごく強いんだそうです。
そして、先ほども出た新山小学校。
全校生徒たった30人で、どこの地域からも入学できる学校です。
さらに、子育て支援センターには、20年も前から保育士さんが常駐していて、保育施設に行く前の子供たちの悩みに答えてくれる・・・
どれをとっても、昔から当たり前のようにやっていたことばかり。
それが、実は全国的に見ると、当たり前ではなくすごいことだった!という事なんですよね~
なんかとってもカッコいいですよね(^-^)
そして今回の受賞、意外な人達が反応しているそうなんです。
それは企業の経営者の皆さん。
ブログなどにこの事を、誇らしく書いてくれる方が多いそうなんです。
それは、伊那小学校のような教育を、今の子供のお父さんお母さんはもちろん、下手すればおじいちゃんおばあちゃんを飛び越えて、ひいおじいちゃん達の頃から受けて育っているんですね。(通知表がないのが、60年も前から続いてるっていう事からも、容易のそれは伺えますよね)
春になると教室はどこもガランとしていて、みんな春探しに野山をかけずり回ってる。
勉強の材料集めに町に出れば、アポなしでも、商店の人も、道行く人も、誰もが相手をしてくれる。
とにかく、地域で子供を育てているという感覚が根付いているのが伊那市なんです。
そのあったかい空気感が点数となって現れているのかもしれませんね。
今回の日本一の田舎とは、ど田舎ではなく、都会の人から見て暮らしやすい田舎の事でした。
伊那小で教育を受けてみたかった思っている 西村容子 でした♡
1/27噂・みんなが知ってる「信濃の国」に、別バージョンがあるんだって!?知ってた??
2015年01月27日
おなじみ、県民なら誰もが歌える「信濃の国」!
以前うわさの調査隊で、
この歌が信大付属長野小学校の校歌でもあることはお伝えしましたが、
今回は「信濃の国」第2弾!
この歌に最近別バージョンが出来たって知ってました?
なぜ?だれが?どうして?なんの為に?謎は深まるばかりです。
まずは真田雁丸屋 代表取締役 塚田 泰裕さんに伺いました。
(塚田さんは歴史戦国グッズ製造販売とともに、省力機械製作会社TIG社長)

「もともとは、上田で「よさこいソーラン」のような
全国規模のダンス大会を開きたいという企画が5年ぐらい前から立ち上がっていて、
そういった有志の方々から相談を受けた。
どうせダンスミュージックを作るなら、上田らしい曲でダンスを踊って欲しいと思い
それなら、長野県民に親しまれている「信濃の国」をということで、
ダンスバージョンの曲にアレンジしてもらった。
詩は私が上田の風景などの題材になる言葉を選んで
それを以前から親交のあった、歴史系アーティスト、歴ドルとして活躍している
『さくらゆき』さんに渡して作詞してしてもらい完成させた。」
実は塚田さんは「信濃の国上田」ダンス実行委員会事務局長でもあります。
元々「信濃の国」は長野県師範学校の教員浅井洌先生の作詞です。
素朴な疑問。著作権などはどうなってる?
「信濃の国」が作られたのが明治時代で、
作者も70年以上も前に亡くなっており著作権は消滅しているそうです。
すでにCD化されているので録音時のエピソードなども伺うと、
たまたま東京に録音を見に行った真田家14代当主・徹さんと塚田さんも、
間奏の合唱で録音参加されたそうです。
参加ミュージシャンも、映画「おくりびと」の
チェロ演奏や主演の本木雅弘の指導をした斉藤孝太郎さんはじめ
有名な方々が上田市の為にと意気に感じて結集されました。
さて、1月30日(金)「信濃の国 上田 ダンスフェスティバル」が
上田駅近くに完成したばかりの「上田 サントミューゼ 大ホール」で開かれます、
皆さん盛り上がってみませんか!
(真ん中は当日出演の劇団G・S・Mの塚田夫人・、左側がダンサー林美帆さん)

入場希望者多数の場合入れ替えがあるかも知れないのでご了承いただきたいとのことです。
「信濃の国」には長野県内の自然や歴史などが沢山盛り込まれていますが、
「信濃の国 上田」のほうにも、上田市内の自然や歴史がいっぱい盛り込まれています。
この歌が、信州上田の魅力や良さを再認識する為のきっかけとなるかも知れませんね。
上田をこよなく愛する住人・根本豊でした
以前うわさの調査隊で、
この歌が信大付属長野小学校の校歌でもあることはお伝えしましたが、
今回は「信濃の国」第2弾!
この歌に最近別バージョンが出来たって知ってました?
なぜ?だれが?どうして?なんの為に?謎は深まるばかりです。
まずは真田雁丸屋 代表取締役 塚田 泰裕さんに伺いました。
(塚田さんは歴史戦国グッズ製造販売とともに、省力機械製作会社TIG社長)


「もともとは、上田で「よさこいソーラン」のような
全国規模のダンス大会を開きたいという企画が5年ぐらい前から立ち上がっていて、
そういった有志の方々から相談を受けた。
どうせダンスミュージックを作るなら、上田らしい曲でダンスを踊って欲しいと思い
それなら、長野県民に親しまれている「信濃の国」をということで、
ダンスバージョンの曲にアレンジしてもらった。
詩は私が上田の風景などの題材になる言葉を選んで
それを以前から親交のあった、歴史系アーティスト、歴ドルとして活躍している
『さくらゆき』さんに渡して作詞してしてもらい完成させた。」
実は塚田さんは「信濃の国上田」ダンス実行委員会事務局長でもあります。
元々「信濃の国」は長野県師範学校の教員浅井洌先生の作詞です。
素朴な疑問。著作権などはどうなってる?
「信濃の国」が作られたのが明治時代で、
作者も70年以上も前に亡くなっており著作権は消滅しているそうです。
すでにCD化されているので録音時のエピソードなども伺うと、
たまたま東京に録音を見に行った真田家14代当主・徹さんと塚田さんも、
間奏の合唱で録音参加されたそうです。
参加ミュージシャンも、映画「おくりびと」の
チェロ演奏や主演の本木雅弘の指導をした斉藤孝太郎さんはじめ
有名な方々が上田市の為にと意気に感じて結集されました。
さて、1月30日(金)「信濃の国 上田 ダンスフェスティバル」が
上田駅近くに完成したばかりの「上田 サントミューゼ 大ホール」で開かれます、
皆さん盛り上がってみませんか!
(真ん中は当日出演の劇団G・S・Mの塚田夫人・、左側がダンサー林美帆さん)

入場希望者多数の場合入れ替えがあるかも知れないのでご了承いただきたいとのことです。
「信濃の国」には長野県内の自然や歴史などが沢山盛り込まれていますが、
「信濃の国 上田」のほうにも、上田市内の自然や歴史がいっぱい盛り込まれています。
この歌が、信州上田の魅力や良さを再認識する為のきっかけとなるかも知れませんね。
上田をこよなく愛する住人・根本豊でした
サミットを軽井沢に!子供たちが選ぶ世界に自慢したい軽井沢のお勧めスポット。
2015年01月26日
2016サミットを軽井沢に!誘致の力になればと軽井沢町にある小中学校で12月からサミット給食が行われています。

サミット給食とは?サミット主要参加国の代表料理・食材を給食にして子供たちに食べてもらい
サミットへの関心。また各国への興味を持ってもらおうと行われています。
前回が1初回。カナダ編。そして、今回はアメリカ編。軽井沢中部小学校にお邪魔しました。

アメリカ編の献立は、自分達で作るハンバーガーとポークビーンズトマトスープ

みんな美味しそうに食べてました。アメリカの食事と言えば!ステーキ・ポテトなどの脂っこいイメージだったようですが、
今回のサミット給食はさっぱり。美味しかったそうです。ただ!思った以上にボリュームがあったようで
最後まで食べるのに苦労していた子もいました。美味しくサミット給食を食べるだけでなく、しっかりアメリカの勉強もした様子。
サミット給食を実施してから、子供たちの中からもサミットが軽井沢で開催されたらと話す子も・・・。
そんな6年生の皆さんに!緊急アンケート。世界に自慢したい軽井沢オススメスポット聞いてみました。
ここで!集計結果発表します。
第5位 旧道・旧軽・銀座通り
第4位 軽井沢の自然
第3位 軽井沢プリンスショッピングプラザ
第2位 浅間山
第1位 風越公園・アイスパーク
以上
このほかにも大賀ホール・図書館・白糸の滝などなど。
子供たちならではのお勧めスポットが聞けました。
調査員 竹井純子

サミット給食とは?サミット主要参加国の代表料理・食材を給食にして子供たちに食べてもらい
サミットへの関心。また各国への興味を持ってもらおうと行われています。
前回が1初回。カナダ編。そして、今回はアメリカ編。軽井沢中部小学校にお邪魔しました。

アメリカ編の献立は、自分達で作るハンバーガーとポークビーンズトマトスープ

みんな美味しそうに食べてました。アメリカの食事と言えば!ステーキ・ポテトなどの脂っこいイメージだったようですが、
今回のサミット給食はさっぱり。美味しかったそうです。ただ!思った以上にボリュームがあったようで
最後まで食べるのに苦労していた子もいました。美味しくサミット給食を食べるだけでなく、しっかりアメリカの勉強もした様子。
サミット給食を実施してから、子供たちの中からもサミットが軽井沢で開催されたらと話す子も・・・。
そんな6年生の皆さんに!緊急アンケート。世界に自慢したい軽井沢オススメスポット聞いてみました。
ここで!集計結果発表します。
第5位 旧道・旧軽・銀座通り
第4位 軽井沢の自然
第3位 軽井沢プリンスショッピングプラザ
第2位 浅間山
第1位 風越公園・アイスパーク
以上
このほかにも大賀ホール・図書館・白糸の滝などなど。
子供たちならではのお勧めスポットが聞けました。
調査員 竹井純子
松本は ほかの地域に比べて はんこ屋さんが めちゃめちゃ多いらしい。
2015年01月23日
私(塚原)は、ず~っと松本に住んでいるもんですから、
これが当たり前だと思っていたんですけどね。
ほかの地域から来た方からよく聞かれるんです。
「なんで松本は、はんこ屋さんがこんなに多いの?」
そうなの???
というわけで、調査してみることにしました。
今回は、ナワテ通りの東口。昔からあるはんこ屋さんへ、聞きに行きましたよ。
鈴木印刻店。

レトロな感じが素敵なお店。
最近は外国人の観光客にも人気なんですって。
ちょうど私が行った時、オーストラリアのシドニーから来たっていう人が、
ハンコを作ってもらっていました。
ワンダフル! ビューティフル! って、とっても嬉しそうでしたよ。

店主の 鈴木 昭男さん。
長野県印章業組合連合会の副会長をつとめていらっしゃいます。
鈴木さんにうかがったところ、確かに松本は、ほかの地域に比べて、
はんこ屋さんが多いんだそうです。
「全国的に見て、松本はやはり、はんこ屋がとても多いようですね。
我々の業界では、だいたい人口3万人に1軒で商売が成り立つと言われているんですが、
人口約24万人の松本市には、20軒以上のはんこ屋がありますから。
特に中心市街地に多く、
全国チェーンのお店より、昔からあるお店が目立って多いのも特徴。」
いったいなぜ、なんでしょうか。
「城下町である松本は、商業も盛んでした。
その中で、親方筋と呼ばれる、職人を育てる大きな店が2軒あったんです。
この2軒で修業した職人がどんどん独立していったために、
多くなったんではないかと思います。」
歴史的な背景があるんですね。
だから、昔からあるお店が多い。
古いお店だと100年。鈴木さんのお店も創業70年になるそうです。
でね。
松本のはんこ屋さん。多いだけじゃなくてね。
全国でもとても珍しい活動をしているんですよ!
「全日本印章業協会っていう組織があるんですけど、
その協会に登録している各地の印章業組合の中でも、
松本印章業組合は、とても熱心な活動をしているんです。
はんこアドバイザーっていう活動で、昨年は市から表彰も受けました。」
はんこアドバイザー???
「実印の印鑑登録は、
その印鑑にその人の名前にない字が入っている場合は登録できません。
大量生産されたものも登録できません。
うっかり登録してしまうと、後でトラブルの原因にもなりうる。
でも、登録の申し込みがあった時に行政でそれを判断することは、なかなか難しいんです。
だから私たちの専門知識を役に立ててほしい、というのが、はんこアドバイザーの活動。
市民課の職員の皆さんと勉強会を開いたり、
疑わしいケースの判別をしたり、ということを日々やっているんです。」
全国でも珍しい活動。もう15年近く続いているそうです。
今では、市の職員の方々もそうとう勉強を重ねてきいるので、
「松本の場合は印鑑登録に関しては全国一、
親切な対応ができるようになっているんですよ。
素晴らしいことだと思います。」
なんか、うれしいですよね。
これは何より、はんこ屋さんが熱い想いを持って活動してきてくれたからこそ。
そしてやはり、松本ははんこ屋さんが多いからこそ、こういう活動が続けてこられた、
ということなんでしょうね。
鈴木さんはね、
「それとね。
いかに、はんこってものが大切なものか。
どういう時に、どういうはんこを使うべきか。
三文判と実印はどう違うのか。捨印はどういう意味があるか。
そういうことをきちんと知ってもらうことが、私たちの使命だと思うんです。」
という想いから、講習会なども積極的に行っているそうです。
今年も松本の「街ゼミ」で5回ぐらい、講習会を開く予定。
詳しい日程は1月31日に発表になるそうです。
あのね、はんこのことって、知らないこと、いっぱいありますよ。
ぜひ、講習会、聞いてください!

ということで。今回の調査では、
松本ははんこ屋さんが多い。だけじゃなく、
熱い想いをもって地域のために活動してくれているはんこ屋さんが多い!
ということがわかりました。
私も講習会、行かなくちゃと本気で思っている、松本の調査隊員 塚原 正子でした。
これが当たり前だと思っていたんですけどね。
ほかの地域から来た方からよく聞かれるんです。
「なんで松本は、はんこ屋さんがこんなに多いの?」
そうなの???
というわけで、調査してみることにしました。
今回は、ナワテ通りの東口。昔からあるはんこ屋さんへ、聞きに行きましたよ。
鈴木印刻店。

レトロな感じが素敵なお店。
最近は外国人の観光客にも人気なんですって。
ちょうど私が行った時、オーストラリアのシドニーから来たっていう人が、
ハンコを作ってもらっていました。
ワンダフル! ビューティフル! って、とっても嬉しそうでしたよ。

店主の 鈴木 昭男さん。
長野県印章業組合連合会の副会長をつとめていらっしゃいます。
鈴木さんにうかがったところ、確かに松本は、ほかの地域に比べて、
はんこ屋さんが多いんだそうです。
「全国的に見て、松本はやはり、はんこ屋がとても多いようですね。
我々の業界では、だいたい人口3万人に1軒で商売が成り立つと言われているんですが、
人口約24万人の松本市には、20軒以上のはんこ屋がありますから。
特に中心市街地に多く、
全国チェーンのお店より、昔からあるお店が目立って多いのも特徴。」
いったいなぜ、なんでしょうか。
「城下町である松本は、商業も盛んでした。
その中で、親方筋と呼ばれる、職人を育てる大きな店が2軒あったんです。
この2軒で修業した職人がどんどん独立していったために、
多くなったんではないかと思います。」
歴史的な背景があるんですね。
だから、昔からあるお店が多い。
古いお店だと100年。鈴木さんのお店も創業70年になるそうです。
でね。
松本のはんこ屋さん。多いだけじゃなくてね。
全国でもとても珍しい活動をしているんですよ!
「全日本印章業協会っていう組織があるんですけど、
その協会に登録している各地の印章業組合の中でも、
松本印章業組合は、とても熱心な活動をしているんです。
はんこアドバイザーっていう活動で、昨年は市から表彰も受けました。」
はんこアドバイザー???
「実印の印鑑登録は、
その印鑑にその人の名前にない字が入っている場合は登録できません。
大量生産されたものも登録できません。
うっかり登録してしまうと、後でトラブルの原因にもなりうる。
でも、登録の申し込みがあった時に行政でそれを判断することは、なかなか難しいんです。
だから私たちの専門知識を役に立ててほしい、というのが、はんこアドバイザーの活動。
市民課の職員の皆さんと勉強会を開いたり、
疑わしいケースの判別をしたり、ということを日々やっているんです。」
全国でも珍しい活動。もう15年近く続いているそうです。
今では、市の職員の方々もそうとう勉強を重ねてきいるので、
「松本の場合は印鑑登録に関しては全国一、
親切な対応ができるようになっているんですよ。
素晴らしいことだと思います。」
なんか、うれしいですよね。
これは何より、はんこ屋さんが熱い想いを持って活動してきてくれたからこそ。
そしてやはり、松本ははんこ屋さんが多いからこそ、こういう活動が続けてこられた、
ということなんでしょうね。
鈴木さんはね、
「それとね。
いかに、はんこってものが大切なものか。
どういう時に、どういうはんこを使うべきか。
三文判と実印はどう違うのか。捨印はどういう意味があるか。
そういうことをきちんと知ってもらうことが、私たちの使命だと思うんです。」
という想いから、講習会なども積極的に行っているそうです。
今年も松本の「街ゼミ」で5回ぐらい、講習会を開く予定。
詳しい日程は1月31日に発表になるそうです。
あのね、はんこのことって、知らないこと、いっぱいありますよ。
ぜひ、講習会、聞いてください!

ということで。今回の調査では、
松本ははんこ屋さんが多い。だけじゃなく、
熱い想いをもって地域のために活動してくれているはんこ屋さんが多い!
ということがわかりました。
私も講習会、行かなくちゃと本気で思っている、松本の調査隊員 塚原 正子でした。
噂の調査隊「受験生必見!伊那谷で転ばないコマ発見!!」
2015年01月22日
先週末、センター試験が終わって、本格的な受験シーズンがスタートしました。
本人はもちろんですが、ご両親や家族は、何もできない分、何か力になれないかと、お守り買ってみたりしちゃいますよね。
そんなあなたにおすすめの話題を今日はお届けします。
今日はちょっと素敵な話を見つけたので、こちらから聞いていただいてもいいですか?
******************
ある日の駅員さんのアナウンス
「駅ホームが一部凍結しており、すべりやす・・・転びやす・・・」
その後沈黙数十秒…。
「失礼しました。
駅ホームが一部凍結しており、すってんころりんしやすくなっております」
と言っていた。
可愛い。
受験生に気を使ってたんだ。
******************
こんな風に世の中全体が、言葉一つでも気を使ってしまうこの時期。
何をしても「転ばない」コマがあったら、ちょっぴりうれしくなっちゃいませんか?
という事で、その噂の転ばないコマを求めて、今回は伊那市に調査に出掛けました。
お邪魔したのは有限会社スワニーさん。
社長の橋爪良博さんに「転ばないコマ」ってどんなものか伺ってみると・・・
「コマと言うのはたいがい低重心で作られているんですが、このコマは高重心に作られていて、回転が効いている間は立ち上がる力が強いので、横から叩いても「それ~!!」って起き上がってくる根性のあるコマですね」
とニコニコ笑顔で答えてくれました。
 笑顔がまぶしい橋爪さん
笑顔がまぶしい橋爪さん
そして、そのコマの名前が「タオレネード」

ここにも書いてあるように
「叩かれたって、負けねーぞ!!」
という気持ちで、自分たちもがんばろうという気持ちを込めて作ったんだそうです。
今回お話伺ったのはスワニーという会社の社長さんですが、そのコマを作っているのは、 設計開発から金型製造、スプリング製造、プラスチック製造、パッケージなど、いくつもの企業の集合体。
「完全地産」を合い言葉に、地元の中小の製造業の方々が集まって、それぞれの自慢の技術を集約して 作られた商品なんです。

その名も「製造業ご当地お土産プロジェクト」
Made in Japan・・・Made in Naganoに拘って作られています。
でも本当に転ばないのか?!
それが気になるところですよね。
そのコマを、実際に転ばないのか回してみました。

↑画像をクリックすると動画が再生します。
何をしたって転ばない。
何をしたって起き上がってくる!って感じですよね。
実は、受験生のためのコマはこれだけではなく、タオレネードの前に作られたかわいいコマもあるんです。
それは「サクラコマ」といって、


一見桜の花のつぼみに見えるんですが・・・

回すとその桜が花開いて、桜の花が回っているように見えるという、とってもかわいいコマなんです。


これも、とても人気らしいんです。
実際、このコマは高遠の弘妙寺さんで、合格祈願をしてもらった、思いの詰まったコマ。
この祈願は、去年から始まったそうなんですが、何百個という単位で祈願するんですが、 足りなくなって増産し、また祈願してというのが去年の状態。
今年はどうなるか楽しみですね。
でもどうしてこんなに変わったコマばかりが、この伊那で製造されているんでしょうか?
その理由を聞いてみると・・・
全国で製造業の技術をアピールして、中小企業同士のネットワークを構築しようと、
「全日本 製造業こま大戦」
と言うものが行われているそうなんです。
250mmの土俵の上で、1対1で自社で作ったコマを戦わせて、負けたらとられちゃう。
優勝者が総取りという大会なんだそうですが、
その大会で評判のよかったコマを、自分たちで売ってみようよという事で、販売を始めたのが、今日ご紹介している数々のコマなんです。
タオレネードもサクラコマも、製造は地元企業が行い、組立や梱包は伊那市の社会福祉協議会で 行われていて、就労支援にも繋がっている商品なんです。
実はこのタオレネードは、その製造コンセプトや、このコマに込められた思いが共感を呼び、 信州プロレスリングのグッヅとして、りんごをイメージした、信州プロレスリングバージョンも発売されているそうです。

プロレスラーの皆さんにも共感を得た、このコマに込められた思い・・・
それはパッケージの後ろにも示されているそうです。
「とっても高精度で作られたコマだけど、子供は無邪気に、大人は無心に回せばいい。
倒れても大丈夫!何度だってやり直せるのだから!!」
と書いてあるんだそうです。
橋爪さんは
「いろんなことがあるけれど、負けねーぞ!負けねーぞ!って立ち上がってもらいたいな」
と話してくれました。
始まったばかりの受験戦争、いろんな思いをしながら戦っていくことと思いますが、タオレネードのようにどんなに叩かれても立ち上がって頑張ってほしいな~と私も思いました。
この転ばないコマ、ネットでも注文ができますし、伊那市役所など各所で売られているそうです。
受験生へのプレゼントにいかがですか!
コマに力をもらった 西村容子 でした♡
本人はもちろんですが、ご両親や家族は、何もできない分、何か力になれないかと、お守り買ってみたりしちゃいますよね。
そんなあなたにおすすめの話題を今日はお届けします。
今日はちょっと素敵な話を見つけたので、こちらから聞いていただいてもいいですか?
******************
ある日の駅員さんのアナウンス
「駅ホームが一部凍結しており、すべりやす・・・転びやす・・・」
その後沈黙数十秒…。
「失礼しました。
駅ホームが一部凍結しており、すってんころりんしやすくなっております」
と言っていた。
可愛い。
受験生に気を使ってたんだ。
******************
こんな風に世の中全体が、言葉一つでも気を使ってしまうこの時期。
何をしても「転ばない」コマがあったら、ちょっぴりうれしくなっちゃいませんか?
という事で、その噂の転ばないコマを求めて、今回は伊那市に調査に出掛けました。
お邪魔したのは有限会社スワニーさん。
社長の橋爪良博さんに「転ばないコマ」ってどんなものか伺ってみると・・・
「コマと言うのはたいがい低重心で作られているんですが、このコマは高重心に作られていて、回転が効いている間は立ち上がる力が強いので、横から叩いても「それ~!!」って起き上がってくる根性のあるコマですね」
とニコニコ笑顔で答えてくれました。
 笑顔がまぶしい橋爪さん
笑顔がまぶしい橋爪さんそして、そのコマの名前が「タオレネード」

ここにも書いてあるように
「叩かれたって、負けねーぞ!!」
という気持ちで、自分たちもがんばろうという気持ちを込めて作ったんだそうです。
今回お話伺ったのはスワニーという会社の社長さんですが、そのコマを作っているのは、 設計開発から金型製造、スプリング製造、プラスチック製造、パッケージなど、いくつもの企業の集合体。
「完全地産」を合い言葉に、地元の中小の製造業の方々が集まって、それぞれの自慢の技術を集約して 作られた商品なんです。

その名も「製造業ご当地お土産プロジェクト」
Made in Japan・・・Made in Naganoに拘って作られています。
でも本当に転ばないのか?!
それが気になるところですよね。
そのコマを、実際に転ばないのか回してみました。

↑画像をクリックすると動画が再生します。
何をしたって転ばない。
何をしたって起き上がってくる!って感じですよね。
実は、受験生のためのコマはこれだけではなく、タオレネードの前に作られたかわいいコマもあるんです。
それは「サクラコマ」といって、


一見桜の花のつぼみに見えるんですが・・・

回すとその桜が花開いて、桜の花が回っているように見えるという、とってもかわいいコマなんです。


これも、とても人気らしいんです。
実際、このコマは高遠の弘妙寺さんで、合格祈願をしてもらった、思いの詰まったコマ。
この祈願は、去年から始まったそうなんですが、何百個という単位で祈願するんですが、 足りなくなって増産し、また祈願してというのが去年の状態。
今年はどうなるか楽しみですね。
でもどうしてこんなに変わったコマばかりが、この伊那で製造されているんでしょうか?
その理由を聞いてみると・・・
全国で製造業の技術をアピールして、中小企業同士のネットワークを構築しようと、
「全日本 製造業こま大戦」
と言うものが行われているそうなんです。
250mmの土俵の上で、1対1で自社で作ったコマを戦わせて、負けたらとられちゃう。
優勝者が総取りという大会なんだそうですが、
その大会で評判のよかったコマを、自分たちで売ってみようよという事で、販売を始めたのが、今日ご紹介している数々のコマなんです。
タオレネードもサクラコマも、製造は地元企業が行い、組立や梱包は伊那市の社会福祉協議会で 行われていて、就労支援にも繋がっている商品なんです。
実はこのタオレネードは、その製造コンセプトや、このコマに込められた思いが共感を呼び、 信州プロレスリングのグッヅとして、りんごをイメージした、信州プロレスリングバージョンも発売されているそうです。

プロレスラーの皆さんにも共感を得た、このコマに込められた思い・・・
それはパッケージの後ろにも示されているそうです。
「とっても高精度で作られたコマだけど、子供は無邪気に、大人は無心に回せばいい。
倒れても大丈夫!何度だってやり直せるのだから!!」
と書いてあるんだそうです。
橋爪さんは
「いろんなことがあるけれど、負けねーぞ!負けねーぞ!って立ち上がってもらいたいな」
と話してくれました。
始まったばかりの受験戦争、いろんな思いをしながら戦っていくことと思いますが、タオレネードのようにどんなに叩かれても立ち上がって頑張ってほしいな~と私も思いました。
この転ばないコマ、ネットでも注文ができますし、伊那市役所など各所で売られているそうです。
受験生へのプレゼントにいかがですか!
コマに力をもらった 西村容子 でした♡
1・20中野市科野小学校の謎の明かりの正体は?
2015年01月20日
中野市でも北に位置する科野小学校。真っ暗な中時よりグランドに謎の明かりが点くらしい??という噂を聞き
早速中野市・科野小学校グランドに行ってみました。街灯もない暗い道を進むと・・・。
グランドを明るく照らすライトが!あ!あのあかりは???
近づいてみると。グランドの隅々まで届いた明かりの中、もくもくとクロスカントリーの練習をする子供たちの姿が!
謎の明かりの正体は、科野小学校クロスカントリークラブの練習のためのナイター設備のあかりでした。

![IMG_0910[1]](http://sbc21.co.jp/blogwp/radikan/files/2015/01/IMG_09101.jpg)
北信濃では冬のシーズンになると小学校のグランドにコースを作ってクロスカントリーの授業が行われます。
中野市でも取材した科野小学校と倭小学校の2校で行われています。が!しかし。学校の施設内にこんな立派なナイター設備が整っているなんて・・・。
本当に珍しい。いったい誰がつけてくれたのか??練習終了後、コーチの湯本浩徳さんにお聞きしました。
この明かりは3年前に地元企業さんと保護者の皆さんの寄付によって設置。それまでは、灯光器の中の練習。
コース全体を照らすことは難しい。足元も暗くなったりと、安全面で心配がありました。
本来ならば、明るい放課後に練習できたらいいのですが、科野小学校クロスカントリークラブは地域クラブとしての活動で
指導者(コーチ)の皆さんのお仕事が終わってからの練習。週2回。夕方6時からの貴重な時間。何とか??明るい中で練習できないものか?
何とかしたいと保護者の皆さんの強い思いで立派なナイター設備が整いました。
そんなお父さん・お母さん・地域の皆さんの思いの中には、地域からいつかオリンピック選手をという思いも。
そんな!大人たちの思いはどれくらい子供たちに届いているのか?
なかなか・・。子供たちのやる気のスイッチは探すのが、難しいようですが、皆さんの思いがいつか!
オリンピック選手輩出となるように・・・・。この背中に期待します。
![IMG_0913[1]](http://sbc21.co.jp/blogwp/radikan/files/2015/01/IMG_09131.jpg)
調査員 竹井純子
早速中野市・科野小学校グランドに行ってみました。街灯もない暗い道を進むと・・・。
グランドを明るく照らすライトが!あ!あのあかりは???
近づいてみると。グランドの隅々まで届いた明かりの中、もくもくとクロスカントリーの練習をする子供たちの姿が!
謎の明かりの正体は、科野小学校クロスカントリークラブの練習のためのナイター設備のあかりでした。

![IMG_0910[1]](http://sbc21.co.jp/blogwp/radikan/files/2015/01/IMG_09101.jpg)
北信濃では冬のシーズンになると小学校のグランドにコースを作ってクロスカントリーの授業が行われます。
中野市でも取材した科野小学校と倭小学校の2校で行われています。が!しかし。学校の施設内にこんな立派なナイター設備が整っているなんて・・・。
本当に珍しい。いったい誰がつけてくれたのか??練習終了後、コーチの湯本浩徳さんにお聞きしました。
この明かりは3年前に地元企業さんと保護者の皆さんの寄付によって設置。それまでは、灯光器の中の練習。
コース全体を照らすことは難しい。足元も暗くなったりと、安全面で心配がありました。
本来ならば、明るい放課後に練習できたらいいのですが、科野小学校クロスカントリークラブは地域クラブとしての活動で
指導者(コーチ)の皆さんのお仕事が終わってからの練習。週2回。夕方6時からの貴重な時間。何とか??明るい中で練習できないものか?
何とかしたいと保護者の皆さんの強い思いで立派なナイター設備が整いました。
そんなお父さん・お母さん・地域の皆さんの思いの中には、地域からいつかオリンピック選手をという思いも。
そんな!大人たちの思いはどれくらい子供たちに届いているのか?
なかなか・・。子供たちのやる気のスイッチは探すのが、難しいようですが、皆さんの思いがいつか!
オリンピック選手輩出となるように・・・・。この背中に期待します。
![IMG_0913[1]](http://sbc21.co.jp/blogwp/radikan/files/2015/01/IMG_09131.jpg)
調査員 竹井純子
1/19噂・軽井沢中学校のサミット給食って、どんな味がするの!?
2015年01月19日
軽井沢中学校で、珍しいネーミングの給食が開発されたと聞いて、早速行ってきました。
その名も「サミット給食」!
サミットってあのサミット?なんで給食?
謎は深まるばかりです。
なにはともあれ軽井沢中学校の現場?に行って、
生徒さんや先生の声を聴いてきました。
メインメニューは
「カナダサーモンのフライ」と「メープルシュガー入りのパン」
(奥皿の左がカナダサーモン、手前がメープルシュガー入りパン)


どちらもカナダの食材を取り入れました。
この給食を考案した、栄養教諭の八巻謙治先生に工夫した点はと尋ねると、
「普段使わない食材なので、生徒たちが美味しく食べてくれるように、食材見本をサンプルとして手に入れて、何度も試した」そうです。
なぜ「サミット給食」なのかを軽井沢中学の小松雅人校長先生に伺うと
(右側・小松校長、左側・北原先生)

「現在軽井沢町は2016年の日本でのサミット開催地の候補として名乗りを上げていて
その一環で子供たちにもサミット参加国の食材に親しんでもらって
その国のことを知ってもらう為に取り入れた。
なぜ最初がカナダの食材かというと、カナダのウィスラーという都市が
軽井沢と姉妹都市なので敬意を表して最初にした」そうです。
この給食の前に、「公民」教科の一環としてサミットについての授業が行われていました。

サミットとは、「頂上」を意味する英語「summit」が由来です。
仏の提唱で1975年から毎年一回、各国の主要都市で開催され(主要先進国首脳会議)、
アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・カナダ・日本に、ロシアの加わった
8か国の首脳およびEU委員長が参加(G7→G8)。
現在の世界の課題とサミットが開催される意義などが、班別に分かれて
「公民」担当の北原憲康先生の指導の下、活発な議論が展開され、
サミットが軽井沢で開催される利点などについても様々な意見が交わされました。
2001.9.11アメリカ同時多発テロ、とその年のサミット開催地・イタリア主要都市であるジェノバに於いて
大規模な抗議デモで紛糾したこと等を受け、
2002年のサミット開催から、カナダの観光都市であるカナナスキスで開催されるなど、
開催地が主要都市から、観光地など比較的テロの対象になりにくい土地に移ってきた流れがある。
また2005年のイギリス開催時(開催地はスコットランド・グレンイーグルズ)に、
ロンドンでのテロで多くの死亡や重傷等の犠牲者が出たことも
この流れをいっそう加速させた。
そういったことも踏まえて、今回軽井沢町が、2016年開催地として名乗りを上げたそうです。
今回のこの「サミット給食」は、サミット誘致活動をしている大人だけでなく、
子供たちにも広く世界的な視野を広げてもらおうと、
昨年12/11に町内3保育所で始まりました。
12/17には軽井沢中学の他に町内3小学校でも実施され、
今後も3月頃まで毎月2回、サミット参加G8のそれぞれの国の
特色ある食材と料理を給食として提供していくそうです。
別な形の食育といいますか、食を通して外国の文化を知ってもらうのがねらいです。
私も実際に給食をいただいてきましたが、いやほんと、旨かったですよ。
私の時代の給食といえばスキムミルク(わかるかナァ)オンリー・の根本豊でした
その名も「サミット給食」!
サミットってあのサミット?なんで給食?
謎は深まるばかりです。
なにはともあれ軽井沢中学校の現場?に行って、

生徒さんや先生の声を聴いてきました。
メインメニューは
「カナダサーモンのフライ」と「メープルシュガー入りのパン」
(奥皿の左がカナダサーモン、手前がメープルシュガー入りパン)


どちらもカナダの食材を取り入れました。
この給食を考案した、栄養教諭の八巻謙治先生に工夫した点はと尋ねると、

「普段使わない食材なので、生徒たちが美味しく食べてくれるように、食材見本をサンプルとして手に入れて、何度も試した」そうです。
なぜ「サミット給食」なのかを軽井沢中学の小松雅人校長先生に伺うと
(右側・小松校長、左側・北原先生)

「現在軽井沢町は2016年の日本でのサミット開催地の候補として名乗りを上げていて
その一環で子供たちにもサミット参加国の食材に親しんでもらって
その国のことを知ってもらう為に取り入れた。
なぜ最初がカナダの食材かというと、カナダのウィスラーという都市が
軽井沢と姉妹都市なので敬意を表して最初にした」そうです。

この給食の前に、「公民」教科の一環としてサミットについての授業が行われていました。

サミットとは、「頂上」を意味する英語「summit」が由来です。
仏の提唱で1975年から毎年一回、各国の主要都市で開催され(主要先進国首脳会議)、
アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・カナダ・日本に、ロシアの加わった
8か国の首脳およびEU委員長が参加(G7→G8)。
現在の世界の課題とサミットが開催される意義などが、班別に分かれて
「公民」担当の北原憲康先生の指導の下、活発な議論が展開され、
サミットが軽井沢で開催される利点などについても様々な意見が交わされました。

2001.9.11アメリカ同時多発テロ、とその年のサミット開催地・イタリア主要都市であるジェノバに於いて
大規模な抗議デモで紛糾したこと等を受け、
2002年のサミット開催から、カナダの観光都市であるカナナスキスで開催されるなど、
開催地が主要都市から、観光地など比較的テロの対象になりにくい土地に移ってきた流れがある。
また2005年のイギリス開催時(開催地はスコットランド・グレンイーグルズ)に、
ロンドンでのテロで多くの死亡や重傷等の犠牲者が出たことも
この流れをいっそう加速させた。
そういったことも踏まえて、今回軽井沢町が、2016年開催地として名乗りを上げたそうです。
今回のこの「サミット給食」は、サミット誘致活動をしている大人だけでなく、
子供たちにも広く世界的な視野を広げてもらおうと、
昨年12/11に町内3保育所で始まりました。
12/17には軽井沢中学の他に町内3小学校でも実施され、
今後も3月頃まで毎月2回、サミット参加G8のそれぞれの国の
特色ある食材と料理を給食として提供していくそうです。
別な形の食育といいますか、食を通して外国の文化を知ってもらうのがねらいです。
私も実際に給食をいただいてきましたが、いやほんと、旨かったですよ。
私の時代の給食といえばスキムミルク(わかるかナァ)オンリー・の根本豊でした
あれ? 松本市には名前に東西南北がつく学校がない! なんで?
2015年01月16日
松本市内の小学校、中学校、そして高校も!
名前に東西南北がつく学校がないんですよ。
他の地域にはありますよね?
何故なんでしょう?
理由があるのか、たまたまなのか。
元松本市立博物館の館長で、松本市史の編纂にたずさわった、
佐藤 玲子さんに聞きました。
82歳っておっしゃっていましたけど、
とってもお元気で素敵な女性でした ♡♡♡

さて。本題。
話は終戦直後にさかのぼります。
昭和22年。学校制度が、今の6・3・3・4・年制に変わりました。
この時に、学校の名前も変わったんです。
長野県の小学校、中学校は、ほとんどが土地の名前を学校名にしました。
松本は同じ地域に学校が2つもなかったから、東西南北を付ける必要がなかった。
あ。開智は別です。これはもう、明治時代からありましたから。
というわけで、開智小学校以外の小・中学校は、地域の名前が学校名になっています。
でね。問題は高校なんです。
それまでの中等学校が、この改革で高校になりました。
で、名前を付けるにあたって。
敗戦国であった日本は、アメリカ軍の占領下になりました。
長野に軍政部があって、その監督下でのこの改革。
軍から条件が出されていたそうです。
それは、
第1、第2など順列をつけるものは名前に使ってはいけない。
男女共学が望ましいから、名前に男子女子もだめ。
この2つ。
これを受けて県からは、地名と方位(東西南北)は使ってもいい、
という条件が出ました。
だから、県内の多くの高校が、地名+東西南北、という名前になったそうです。
長野西、伊那北、というぐあいにね。
ところが。
松本の場合は特別な事情がありまして。
<その1>
昭和20年ぐらいの松本は、ほかの地域に比べて、中等学校がとても多かったんです。
県立の中等学校が5つ。市立が2つ。
そして私立の松本商業学校や、そのほかにも実業学校もあって、
とにかく多かった。
<その2>
その上の高等学校も充実していた。
大正時代からある松本高等学校、医学専門学校(医専)、
さらに、長野県の女性の最高学府である松本女子師範学校。
つまり・・・ものすごく厚い教育体制がすでにあった。
でね。
こういう事情があって、
教育、学校に対する想いがとても熱かった土地柄なもんだから、
学校の名前にも、相当なこだわりがあったらしいんです。
「あのね、どの学校もみんな、松本をつけたかったの。
でも、松本高等学校っていう名門校があったから、
松本高校ってやるわけにいかないのよ(笑)。だから困っちゃって。
どの学校もそれはもう一生懸命、真剣に考えたのね。」
その結果。
松本の古い、由緒ある地名を使って、それを松本にくっつけた。
松本深志高校、松本県が丘高校、松本蟻ケ崎高校・・・。
当時の高校の名前はすべて、「松本」で始まるんです。
「つまりね。学校の数も、思い入れも、
東西南北だけじゃ足りなかったのね。
それだけ、学校に対して、教育に対して、熱い想いがあったのね。
それぞれの学校の100年史や90年史には、
その想いが、ちゃんと記録されているはずよ。
学校へ行けば見られるから、ぜひご覧になってみてください。」
と佐藤さん。
松本市民としては、とってもありがたいお話。
そして、後世にしっかりと伝えていきたいお話だと思います。
余談なんですが。
佐藤さん。
まさにこの終戦直後、松本の学生さんだったんです。
昭和24年。男女共学になった松本深志高校の、
初代女子生徒、なんですよ!
「あのころはね~・・・」
楽しくて貴重なお話をたくさんたくさん、聞かせて頂きました。
ありがとうございました!!
もっと勉強しなくちゃ、もっとちゃんとしなくちゃ。佐藤さんのような素敵な女性に憧れている、松本の調査隊員 塚原 正子でした。
名前に東西南北がつく学校がないんですよ。
他の地域にはありますよね?
何故なんでしょう?
理由があるのか、たまたまなのか。
元松本市立博物館の館長で、松本市史の編纂にたずさわった、
佐藤 玲子さんに聞きました。
82歳っておっしゃっていましたけど、
とってもお元気で素敵な女性でした ♡♡♡

さて。本題。
話は終戦直後にさかのぼります。
昭和22年。学校制度が、今の6・3・3・4・年制に変わりました。
この時に、学校の名前も変わったんです。
長野県の小学校、中学校は、ほとんどが土地の名前を学校名にしました。
松本は同じ地域に学校が2つもなかったから、東西南北を付ける必要がなかった。
あ。開智は別です。これはもう、明治時代からありましたから。
というわけで、開智小学校以外の小・中学校は、地域の名前が学校名になっています。
でね。問題は高校なんです。
それまでの中等学校が、この改革で高校になりました。
で、名前を付けるにあたって。
敗戦国であった日本は、アメリカ軍の占領下になりました。
長野に軍政部があって、その監督下でのこの改革。
軍から条件が出されていたそうです。
それは、
第1、第2など順列をつけるものは名前に使ってはいけない。
男女共学が望ましいから、名前に男子女子もだめ。
この2つ。
これを受けて県からは、地名と方位(東西南北)は使ってもいい、
という条件が出ました。
だから、県内の多くの高校が、地名+東西南北、という名前になったそうです。
長野西、伊那北、というぐあいにね。
ところが。
松本の場合は特別な事情がありまして。
<その1>
昭和20年ぐらいの松本は、ほかの地域に比べて、中等学校がとても多かったんです。
県立の中等学校が5つ。市立が2つ。
そして私立の松本商業学校や、そのほかにも実業学校もあって、
とにかく多かった。
<その2>
その上の高等学校も充実していた。
大正時代からある松本高等学校、医学専門学校(医専)、
さらに、長野県の女性の最高学府である松本女子師範学校。
つまり・・・ものすごく厚い教育体制がすでにあった。
でね。
こういう事情があって、
教育、学校に対する想いがとても熱かった土地柄なもんだから、
学校の名前にも、相当なこだわりがあったらしいんです。
「あのね、どの学校もみんな、松本をつけたかったの。
でも、松本高等学校っていう名門校があったから、
松本高校ってやるわけにいかないのよ(笑)。だから困っちゃって。
どの学校もそれはもう一生懸命、真剣に考えたのね。」
その結果。
松本の古い、由緒ある地名を使って、それを松本にくっつけた。
松本深志高校、松本県が丘高校、松本蟻ケ崎高校・・・。
当時の高校の名前はすべて、「松本」で始まるんです。
「つまりね。学校の数も、思い入れも、
東西南北だけじゃ足りなかったのね。
それだけ、学校に対して、教育に対して、熱い想いがあったのね。
それぞれの学校の100年史や90年史には、
その想いが、ちゃんと記録されているはずよ。
学校へ行けば見られるから、ぜひご覧になってみてください。」
と佐藤さん。
松本市民としては、とってもありがたいお話。
そして、後世にしっかりと伝えていきたいお話だと思います。
余談なんですが。
佐藤さん。
まさにこの終戦直後、松本の学生さんだったんです。
昭和24年。男女共学になった松本深志高校の、
初代女子生徒、なんですよ!
「あのころはね~・・・」
楽しくて貴重なお話をたくさんたくさん、聞かせて頂きました。
ありがとうございました!!
もっと勉強しなくちゃ、もっとちゃんとしなくちゃ。佐藤さんのような素敵な女性に憧れている、松本の調査隊員 塚原 正子でした。
噂の調査隊「あなたの姫度は?女性限定のおみくじとは!!」
2015年01月15日
神社やお寺に行くとついつい引きたくなってしまう「おみくじ」
吉凶に一喜一憂しながら、木の枝などにくくり付けておしまいってパターン多くないですか?
今回は、おみくじの意外な姿まで調査できちゃいましたよ!!!
実は、南信州 阿智村に女性限定のちょっと変わったおみくじがあるという事で、今日は、阿智村園原にある「信濃比叡 広拯院(こうじょういん)」に調査に出掛けてきました。
広拯院(こうじょういん)は、平安時代初期、東山道最大の難所と言われた神坂峠に、最澄(伝教大師)が建てた布施屋(旅人の宿泊場)が始まり。
今は、月見堂としてその建物跡が残されていますが、1200年という歴史を誇るお寺です。
そのお寺の副住職 岡田暁光さんに、それはどんなおみくじなのか伺いました。
そのおみくじとは、こちら!

こちらが岡田副住職さん(^o^;;)
その手元にある、こちら!!!

「姫みくじ」
女性のための、女性限定のおみくじなんです。
女性の外見ばかりでなく、内面も磨いてほしいという事で、女性に必要な教えの数々が修められているそうです。
その中身をちょっとご紹介しますね♡
まずは、なんといってもこちら!

あなたの姫度は何パーセント?
という事で、あなたの今の女性らしさが数字で示されています。
さらに・・・


「理想の殿方」のタイプに、あなたをを歴史上の女性になぞらえると何?という事で、あなたがどんな魅力を持った女性かが示されています。
そして、最後には・・・

こちら!「お叱りの言葉」ということで、より姫度を上げるためのアドバイスも書かれています。
キッシーのおみくじを代わりに引いてきたんですが、
OAの中で開いてみると、
キッシーの姫度は・・・・・末吉の「70%」だったようです。
そもそもこのおみくじがどうしてここで引けるようになったかというと・・・
一つは昼神温泉で行われている「女子旅」の企画に沿う形で始められたそうですが、
この辺りの歴史にも大きく影響を受けているようなんです。
ここ園原は、源氏物語のゆかりの地。
源氏物語と言えば女性の色恋の話がたくさん出てきます。
ですから、この園原の地で、女性が美しくなるための・・・
いわゆる「女子力」を上げてもらうためのお示しができたらな~
と言うのが副住職様の思いなんだそうです。
その日は、飯田からお越しの女子二人組が
「姫みくじ、引いてみたい」
という事だったので、ちょこっとのぞかせていただいてしまいました。
まず、本堂の隅に置かれた「姫みくじ」


こんな感じで置かれているのですが・・・

そこから、自分の好みのおみくじを選びます。
お一人は、「さっきから気になっていたので」と、ずいぶん下の方から黄色のおみくじを。
もうお一人は、「直感で」と、一番上にあったピンクのおみくじを。
開いていただくと、お一人は姫度70%、もうお一人は姫度95%でした。
お二人とも満足気で、その下の文面にキャッキャ言いながら読み進めていました☆
そして・・・
「普通のおみくじ引くより楽しい~女の子は是非引いてもらいたいと思いました(^-^)v」
と話してくださいました。
さらに!!このお寺ですごいことを教えていただいちゃったんです!!!
あなたは、おみくじって、本来どんなものだったのかご存知ですか?
広拯院には、おみくじののことをよく知る、おみくじのエキスパートとでも言いましょうか・・・そんなすごい方がいらっしゃったんです。
こちらの尼僧様 入山光澄さんがその方。

入山さんによると・・・
比叡山延暦寺の横川に元三大師堂と言って、第18代天台座主・慈恵大師良源が開かれたお寺があり、そこがおみくじの発祥の地だという事なんです。
実は江戸時代にある大僧正の夢枕に元三大師様が立ち
「おみくじせんの元が、戸隠神社の奥社にあるので、それを取ってきてやりなさい」
と言ったそうなんです。
それが、おみくじの元!!
という事は・・・
戸隠神社がおみくじの元の元?!?!?!
長野県すご~~~~~い!!!
しかも、元々おみくじは、物事をなす大きな決断の時に、引いていたもので、
おみくじを引くときには、観音行を33回あげて、本当にその人にとって必要かどうかを確認して、神仏のご加護の元に引いたものなんだそうです。
こうしたおみくじで、世を動かしてきた歴史上の人物もいるんですって(*0*)
そして、ここ広拯院は、そんな元来のおみくじを引いてくれるお寺でもあるそうなんです。
それは、入山さん自身がその元三大師堂でおみくじの修行をしてきた方だからできること。
すごい尼僧様が、ここにはいらっしゃるんですね!!!
入山さんのお顔を拝すると、悩み事でもなんでも話したくなってしまいますよ!!!
私もいっぱい話、聞いてもらっちゃいました。
このお寺は、皆さんの実家なんですって!
「いつでも帰っていらっしゃい(^-^)」
と笑顔でおっしゃる言葉に涙が流れました。
さてさて、最後に
おみくじって、引いたらその場で木などにくくり付けてきてしまいますよね。
でも広拯院の姫みくじは、持って帰ってもらうんだそうです。
それは、大吉、小吉などその吉凶が大事なのではなく、そこに書いてある文面をよく読んで、その後の生活に生かしてもらいたいから・・・
おみくじをお守りのように身に付けて、気になった時に読み返す。
そして、1年後に、感謝の気持ちと共に、お炊き上げなどにもって行く。
もしかしたら、この方が本来の形なんじゃないかと、私は思ってしまいました。
今回は驚きの発見の多い調査でした☆☆☆
また、実家だという広拯院に帰りたくなっている 西村容子 でした♡
吉凶に一喜一憂しながら、木の枝などにくくり付けておしまいってパターン多くないですか?
今回は、おみくじの意外な姿まで調査できちゃいましたよ!!!
実は、南信州 阿智村に女性限定のちょっと変わったおみくじがあるという事で、今日は、阿智村園原にある「信濃比叡 広拯院(こうじょういん)」に調査に出掛けてきました。
広拯院(こうじょういん)は、平安時代初期、東山道最大の難所と言われた神坂峠に、最澄(伝教大師)が建てた布施屋(旅人の宿泊場)が始まり。
今は、月見堂としてその建物跡が残されていますが、1200年という歴史を誇るお寺です。
そのお寺の副住職 岡田暁光さんに、それはどんなおみくじなのか伺いました。
そのおみくじとは、こちら!

こちらが岡田副住職さん(^o^;;)
その手元にある、こちら!!!

「姫みくじ」
女性のための、女性限定のおみくじなんです。
女性の外見ばかりでなく、内面も磨いてほしいという事で、女性に必要な教えの数々が修められているそうです。
その中身をちょっとご紹介しますね♡
まずは、なんといってもこちら!

あなたの姫度は何パーセント?
という事で、あなたの今の女性らしさが数字で示されています。
さらに・・・


「理想の殿方」のタイプに、あなたをを歴史上の女性になぞらえると何?という事で、あなたがどんな魅力を持った女性かが示されています。
そして、最後には・・・

こちら!「お叱りの言葉」ということで、より姫度を上げるためのアドバイスも書かれています。
キッシーのおみくじを代わりに引いてきたんですが、
OAの中で開いてみると、
キッシーの姫度は・・・・・末吉の「70%」だったようです。
そもそもこのおみくじがどうしてここで引けるようになったかというと・・・
一つは昼神温泉で行われている「女子旅」の企画に沿う形で始められたそうですが、
この辺りの歴史にも大きく影響を受けているようなんです。
ここ園原は、源氏物語のゆかりの地。
源氏物語と言えば女性の色恋の話がたくさん出てきます。
ですから、この園原の地で、女性が美しくなるための・・・
いわゆる「女子力」を上げてもらうためのお示しができたらな~
と言うのが副住職様の思いなんだそうです。
その日は、飯田からお越しの女子二人組が
「姫みくじ、引いてみたい」
という事だったので、ちょこっとのぞかせていただいてしまいました。
まず、本堂の隅に置かれた「姫みくじ」


こんな感じで置かれているのですが・・・

そこから、自分の好みのおみくじを選びます。
お一人は、「さっきから気になっていたので」と、ずいぶん下の方から黄色のおみくじを。
もうお一人は、「直感で」と、一番上にあったピンクのおみくじを。
開いていただくと、お一人は姫度70%、もうお一人は姫度95%でした。
お二人とも満足気で、その下の文面にキャッキャ言いながら読み進めていました☆
そして・・・
「普通のおみくじ引くより楽しい~女の子は是非引いてもらいたいと思いました(^-^)v」
と話してくださいました。
さらに!!このお寺ですごいことを教えていただいちゃったんです!!!
あなたは、おみくじって、本来どんなものだったのかご存知ですか?
広拯院には、おみくじののことをよく知る、おみくじのエキスパートとでも言いましょうか・・・そんなすごい方がいらっしゃったんです。
こちらの尼僧様 入山光澄さんがその方。

入山さんによると・・・
比叡山延暦寺の横川に元三大師堂と言って、第18代天台座主・慈恵大師良源が開かれたお寺があり、そこがおみくじの発祥の地だという事なんです。
実は江戸時代にある大僧正の夢枕に元三大師様が立ち
「おみくじせんの元が、戸隠神社の奥社にあるので、それを取ってきてやりなさい」
と言ったそうなんです。
それが、おみくじの元!!
という事は・・・
戸隠神社がおみくじの元の元?!?!?!
長野県すご~~~~~い!!!
しかも、元々おみくじは、物事をなす大きな決断の時に、引いていたもので、
おみくじを引くときには、観音行を33回あげて、本当にその人にとって必要かどうかを確認して、神仏のご加護の元に引いたものなんだそうです。
こうしたおみくじで、世を動かしてきた歴史上の人物もいるんですって(*0*)
そして、ここ広拯院は、そんな元来のおみくじを引いてくれるお寺でもあるそうなんです。
それは、入山さん自身がその元三大師堂でおみくじの修行をしてきた方だからできること。
すごい尼僧様が、ここにはいらっしゃるんですね!!!
入山さんのお顔を拝すると、悩み事でもなんでも話したくなってしまいますよ!!!
私もいっぱい話、聞いてもらっちゃいました。
このお寺は、皆さんの実家なんですって!
「いつでも帰っていらっしゃい(^-^)」
と笑顔でおっしゃる言葉に涙が流れました。
さてさて、最後に
おみくじって、引いたらその場で木などにくくり付けてきてしまいますよね。
でも広拯院の姫みくじは、持って帰ってもらうんだそうです。
それは、大吉、小吉などその吉凶が大事なのではなく、そこに書いてある文面をよく読んで、その後の生活に生かしてもらいたいから・・・
おみくじをお守りのように身に付けて、気になった時に読み返す。
そして、1年後に、感謝の気持ちと共に、お炊き上げなどにもって行く。
もしかしたら、この方が本来の形なんじゃないかと、私は思ってしまいました。
今回は驚きの発見の多い調査でした☆☆☆
また、実家だという広拯院に帰りたくなっている 西村容子 でした♡

















